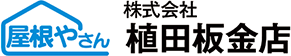屋根からの雨漏り修理のDIYはおすすめできない!リスクを解説

生活に支障がないからといって、放置すると被害が拡大する恐れがあります。
雨漏りは自然に直るものではないため、放置する時間が長いと二次被害につながり、修理費用も高くなるでしょう。
本記事では、雨漏りを放置するとどのような危険性があるのか解説します。
信頼できる業者の選び方も解説するので、雨漏りの修理でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
屋根からの雨漏りでやってほしい応急処置

・バケツやタオルで水を受け止める
・防水テープで浸入口を塞ぐ
・ブルーシートを屋根に被せる
・コーキングで雨漏り箇所を埋める
応急処置をすると、被害を最小限に抑えて修理までの間の時間を稼げます。
ただし、応急処置はあくまで一時的なもので、できるだけ早く専門業者に修理を依頼するのがおすすめです。
バケツやタオルで水を受け止める
天井から水が漏れている場合、その下にバケツや洗面器などの容器を置き、落ちてくる水を受け止めましょう。
水が床に落ちて広がるのを防ぐため、バケツの周囲や水が落ちている場所にタオルや雑巾を敷くのも効果的です。
タオルが水を吸収するので、床や家具が水浸しになるのを防ぎ、二次的な被害を抑えられます。
水が床に落ちて広がるのを防ぐため、バケツの周囲や水が落ちている場所にタオルや雑巾を敷くのも効果的です。
タオルが水を吸収するので、床や家具が水浸しになるのを防ぎ、二次的な被害を抑えられます。
防水テープで浸入口を塞ぐ
防水テープで雨水の浸入口を塞ぐのは、手軽で便利な応急処置法の1つです。
使用の注意点として、防水テープを貼る部分を清掃してから、防水テープで浸入口を防ぎましょう。
雨漏りの原因箇所に汚れやホコリ、油分が残っていると、テープがしっかりと密着せずに防水効果が低下するからです。
あくまでも一時的な対策なので、時間が経つと劣化して防水効果が薄れるので注意してください。
使用の注意点として、防水テープを貼る部分を清掃してから、防水テープで浸入口を防ぎましょう。
雨漏りの原因箇所に汚れやホコリ、油分が残っていると、テープがしっかりと密着せずに防水効果が低下するからです。
あくまでも一時的な対策なので、時間が経つと劣化して防水効果が薄れるので注意してください。
ブルーシートを屋根に被せる
屋根の雨漏り箇所にブルーシートをかけて、一時的に雨水の浸入を防ぐのも有効です。
ブルーシートを屋根全体にかぶせたら、シートがずれないようにロープや重りでしっかりと固定しましょう。
ただし屋根の作業は高所で行うため、非常に危険です。
屋根の傾斜や天候条件によっては転落のリスクが高いため、自分一人で行うのは避けた方が良いでしょう。
ブルーシートを屋根全体にかぶせたら、シートがずれないようにロープや重りでしっかりと固定しましょう。
ただし屋根の作業は高所で行うため、非常に危険です。
屋根の傾斜や天候条件によっては転落のリスクが高いため、自分一人で行うのは避けた方が良いでしょう。
コーキングで雨漏り箇所を埋める
屋根材の接合部や壁の取り合い部分に小さな隙間や亀裂ができている場合、コーキングでその隙間を埋めれば雨水の浸入を防げます。
瓦屋根の棟部分や金属屋根の釘穴周りなど、比較的小さな範囲での漏水であればコーキングは効果的です。
しかし屋根材や下地が大きく劣化している場合、コーキングで隙間を埋めても根本的な解決にはなりません。
雨漏りの原因が不明確な場合や屋根全体に問題がある場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。
瓦屋根の棟部分や金属屋根の釘穴周りなど、比較的小さな範囲での漏水であればコーキングは効果的です。
しかし屋根材や下地が大きく劣化している場合、コーキングで隙間を埋めても根本的な解決にはなりません。
雨漏りの原因が不明確な場合や屋根全体に問題がある場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。
屋根の雨漏りを自分で修理(DIY)するのはおすすめできない

しかし素人が修理を行うと、屋根材を傷つけて新たな不具合が発生する恐れがあります。
屋根から落下してケガをするリスクもあるため、おすすめできません。
適切な修理ができなければ、改めて業者に修理を依頼する必要があります。
修理費用を抑えたいのであれば、補助金や助成金を活用できる場合があります。
自治体によって条件が異なるため、お住まいの地域ではどのような内容になっているか確認しましょう。
屋根の雨漏り発生原因を探す方法

・目視による調査
・散水調査
・紫外線投射発光調査
・赤外線サーモグラフィー調査
それぞれの方法について解説します。
目視による調査
目視による調査は、雨漏り調査の専門家が屋根や外壁、室内を目で見て雨漏りした箇所を確認する方法です。
簡単に実施できて、調査費用が抑えられます。
しかし外見だけでわかる範囲に限られるため、原因が正確に特定できない場合もあるので注意してください。
簡単に実施できて、調査費用が抑えられます。
しかし外見だけでわかる範囲に限られるため、原因が正確に特定できない場合もあるので注意してください。
散水調査
散水調査は雨漏りが疑われる箇所に水を撒いて、どこから雨水が浸入するかを確認する方法です。
実際の雨と同じ状況を再現できるため、雨漏りの原因を特定しやすくなります。
ただし実際の状況を再現するため、時間がかかるのがデメリットです。
実際の雨と同じ状況を再現できるため、雨漏りの原因を特定しやすくなります。
ただし実際の状況を再現するため、時間がかかるのがデメリットです。
紫外線投射発光調査
紫外線投射発光調査は発光液を屋根や壁に塗布し、紫外線を当てて雨水の浸入経路を確認する方法です。
発光液が光ることで、雨水の流れが視覚化できるため、屋根の間の見えにくい隙間などで発生した雨漏りも把握できます。
しかし特殊な機材が必要なため、調査費用が高くなる場合もあります。
発光液が光ることで、雨水の流れが視覚化できるため、屋根の間の見えにくい隙間などで発生した雨漏りも把握できます。
しかし特殊な機材が必要なため、調査費用が高くなる場合もあります。
赤外線サーモグラフィー調査
赤外線サーモグラフィー調査は赤外線カメラを使って温度差を測定し、雨水が浸入している箇所を特定する方法です。
壁や天井の内部構造など見えない部分の水分を検出できるため、非常に精度の高い調査が期待できます。
ただし紫外線投射発光調査と同様にコストが高いため、調査費用が高額になりがちです。
壁や天井の内部構造など見えない部分の水分を検出できるため、非常に精度の高い調査が期待できます。
ただし紫外線投射発光調査と同様にコストが高いため、調査費用が高額になりがちです。
屋根で雨漏りが起こりやすい場所

・谷樋
・屋根材の継ぎ目や接合部
・屋根と壁の取り合い部分
・天窓の周辺
それぞれの箇所について詳しく解説します。
屋根の谷樋
屋根の谷樋は、屋根の傾斜面が交わる谷状の部分に設置される樋で、屋根の上を流れる雨水が集まりやすい場所です。
谷樋部分は排水が集中するため、ゴミや落ち葉が溜まると排水が滞り、雨水が溜まりやすくなります。
詰まると雨水があふれ、屋根内部に水が浸入して雨漏りを引き起こすので注意しましょう。
谷樋部分は排水が集中するため、ゴミや落ち葉が溜まると排水が滞り、雨水が溜まりやすくなります。
詰まると雨水があふれ、屋根内部に水が浸入して雨漏りを引き起こすので注意しましょう。
屋根材の継ぎ目や接合部
屋根材同士の継ぎ目や接合部は、特に雨水が浸入しやすい場所です。
特にスレート屋根や金属屋根では、経年劣化により接合部に隙間が生じると、そこから雨水が浸入して雨漏りになります。
特にスレート屋根や金属屋根では、経年劣化により接合部に隙間が生じると、そこから雨水が浸入して雨漏りになります。
屋根と壁の取り合い部分
屋根と外壁が接する取り合いと呼ばれる部分は、雨水が流れ込みやすいです。
取り合い部分のモルタルやコーキングが劣化すると、雨水が浸入しやすくなり、雨漏りのリスクが高まります。
取り合い部分のモルタルやコーキングが劣化すると、雨水が浸入しやすくなり、雨漏りのリスクが高まります。
天窓の周辺
屋根に突き出した構造物である天窓や、煙突の周辺も雨漏りが発生しやすいです。
防水処理が不十分だと、天窓の隙間から雨水が浸入し、雨漏りの原因になります。
雨漏りを防ぐためには、定期的な点検と適切なメンテナンスを心がけましょう。
防水処理が不十分だと、天窓の隙間から雨水が浸入し、雨漏りの原因になります。
雨漏りを防ぐためには、定期的な点検と適切なメンテナンスを心がけましょう。
屋根からの雨漏りの修理方法

・屋根材
・屋根の棟
・雨樋
・天窓
・陸屋根
それぞれの特徴について解説します。
屋根材の修理
屋根材の劣化や破損によって、雨漏りを引き起こすことがあります。
スレートや瓦、金属屋根など、屋根材の種類に応じて修理方法が異なるので注意しましょう。
破損した屋根材を交換する、ヒビ割れた部分を補修する、浮き上がった屋根材を固定し直すなどの方法で修理するのが一般的です。
もし屋根全体が劣化している場合は、屋根材の全面交換や葺き替えが必要になります。
スレートや瓦、金属屋根など、屋根材の種類に応じて修理方法が異なるので注意しましょう。
破損した屋根材を交換する、ヒビ割れた部分を補修する、浮き上がった屋根材を固定し直すなどの方法で修理するのが一般的です。
もし屋根全体が劣化している場合は、屋根材の全面交換や葺き替えが必要になります。
屋根の棟の修理
屋根の棟(屋根の頂上部分)は、風雨にさらされやすいので、雨漏りの原因になります。
棟板金の浮きやズレが主な原因のため、棟板金の浮きやズレを修正してきちんと固定しましょう。
棟の下地が劣化している場合は、下地の補修や交換が必要です。
棟板金の浮きやズレが主な原因のため、棟板金の浮きやズレを修正してきちんと固定しましょう。
棟の下地が劣化している場合は、下地の補修や交換が必要です。
雨樋の修理
雨樋の詰まりや破損により、雨水が適切に排水されず、屋根から壁や建物内部に水が漏れる原因となります。
定期的に雨樋に詰まっているゴミや落ち葉を取り除き、雨樋を清掃しましょう。
雨樋の傾斜が不適切な場合は、正しい角度に調整してもらうように業者に依頼してください。
定期的に雨樋に詰まっているゴミや落ち葉を取り除き、雨樋を清掃しましょう。
雨樋の傾斜が不適切な場合は、正しい角度に調整してもらうように業者に依頼してください。
天窓の修理
天窓は、コーキングの劣化や設置不良が原因で雨水が浸入しやすくなります。
天窓周辺の防水処理を再度行うことで、雨水の浸入を防げるため、劣化したコーキングを除去して新しいコーキングを施工しましょう。
天窓自体が劣化している場合は、天窓の交換が必要です。
天窓周辺の防水処理を再度行うことで、雨水の浸入を防げるため、劣化したコーキングを除去して新しいコーキングを施工しましょう。
天窓自体が劣化している場合は、天窓の交換が必要です。
陸屋根の修理
陸屋根は雨水が溜まりやすく、防水層が劣化すると雨漏りが発生する確率が高くなります。
主な雨漏りの原因は、陸屋根のヒビ割れや防水層の剥がれです。
ヒビ割れた箇所は、コーキング剤で埋めて防水処理を施しましょう。
主な雨漏りの原因は、陸屋根のヒビ割れや防水層の剥がれです。
ヒビ割れた箇所は、コーキング剤で埋めて防水処理を施しましょう。
屋根の雨漏り修理は火災保険を適用できる場合がある

火災保険によっては風災・雪災・雹災といった自然災害による雨漏りの修理が、補償の対象に含まれているからです。
住宅火災保険より住宅総合保険の方が、住宅に関するあらゆるトラブルに対してまとまった補償を受けられます。
大雨や台風などの後に雨漏りが生じた場合は、補償対象になるか保険会社に確認しましょう。
ただし、経年劣化が原因の雨漏りは対象外です。
火災保険が適用できる期間が定められているため、確認や申請は早めに行いましょう。
屋根の雨漏り修理は補助金・助成金が使える場合がある

雨漏り修理も例外ではなく、補助金や助成金の対象となるかもしれません。
耐震補強や高齢者向けの住宅改修、省エネ改修などと関連している場合には、補助金や助成金が支給される可能性が高いです。
利用できる補助金や助成金があるかどうかは、自治体に確認するのがおすすめです。
屋根の雨漏り修理を依頼する業者のポイント

・資格、実績があるか
・見積書の内容が詳しいか
・アフターフォローがしっかりしているか
それぞれのポイントを解説します。
資格・実績があるか
雨漏りの実地検査や修理には、専門知識が必要です。
建設板金基幹技能者や雨漏り検診士といった、専門資格をもつ作業者が在籍する業者を選ぶと安心です。
もしくは、雨漏りに関する施工実績があるかどうか確認しましょう。
実績が多いほど経験が豊富で、たしかな技術力がある業者といえます。
建設板金基幹技能者や雨漏り検診士といった、専門資格をもつ作業者が在籍する業者を選ぶと安心です。
もしくは、雨漏りに関する施工実績があるかどうか確認しましょう。
実績が多いほど経験が豊富で、たしかな技術力がある業者といえます。
見積書の内容が詳しいか
見積書の内容が詳しく書かれている業者は、誠実で信頼できます。
専門知識のない素人が見ても、何のための費用か、どのような材料を使うのか理解できるくらい詳細な内容が望ましいです。
「一式」といった表記で、何についての費用かわからない場合は、そのままにせず説明してもらいましょう。
曖昧なままにしておくと、施工後に高額な費用を請求されるケースもあります。
トラブルを避けるためにも、しっかりと見積書を確認しましょう。
専門知識のない素人が見ても、何のための費用か、どのような材料を使うのか理解できるくらい詳細な内容が望ましいです。
「一式」といった表記で、何についての費用かわからない場合は、そのままにせず説明してもらいましょう。
曖昧なままにしておくと、施工後に高額な費用を請求されるケースもあります。
トラブルを避けるためにも、しっかりと見積書を確認しましょう。
アフターフォローがしっかりしているか
専門知識があり雨漏り修理の実績が豊富な業者でも、一度の施工で完全に直せるとは限りません。
施工後に、思わぬ場所から雨水が浸入するケースも考えられます。
万が一の可能性を考えて、アフターフォローがしっかりしている業者を選ぶと安心です。
一定期間の無料補修保証があるかどうか、事前に確認しましょう。
施工後に、思わぬ場所から雨水が浸入するケースも考えられます。
万が一の可能性を考えて、アフターフォローがしっかりしている業者を選ぶと安心です。
一定期間の無料補修保証があるかどうか、事前に確認しましょう。
屋根の雨漏り修理が必要になる原因

・屋根の経年劣化
・屋根の破損
・業者の施工不良
それぞれ詳しく解説します。
屋根の経年劣化
屋根材には寿命があるため、経年劣化によって割れ・ヒビが生じ、雨漏りにつながる可能性があります。
湿気によって建物にカビが発生し、木材部分が腐食しているケースも考えられます。
屋根材の寿命には目安もありますが、建物の建て方・築年数・環境によっても左右されると考えましょう。
定期的なメンテナンスや塗装によって、屋根材を長持ちさせることも可能です。
湿気によって建物にカビが発生し、木材部分が腐食しているケースも考えられます。
屋根材の寿命には目安もありますが、建物の建て方・築年数・環境によっても左右されると考えましょう。
定期的なメンテナンスや塗装によって、屋根材を長持ちさせることも可能です。
屋根の破損
台風などの強い風で瓦が飛ばされたり、飛行物で穴が開いたりすると屋根が破損するため雨漏りが発生する可能性があります。
雪が多い地域では、積雪の重さで屋根が破損するケースもあります。
屋根はそれぞれの屋根材が葺かれて形成されているため、ずれたり剥がれたりすると、隙間から雨水が浸入しやすくなるため注意が必要です。
雪が多い地域では、積雪の重さで屋根が破損するケースもあります。
屋根はそれぞれの屋根材が葺かれて形成されているため、ずれたり剥がれたりすると、隙間から雨水が浸入しやすくなるため注意が必要です。
業者の施工不良
屋根と外壁の工事を異なる業者が手がけた場合、屋根と外壁が接着している部分から雨水が漏れるケースがあります。
業者が手抜き工事やミスをしたため、新築やリフォーム直後でも雨漏りするケースもあるので注意が必要です。
費用を抑えたいからと、料金の安い業者を選ぶと手抜き工事が行われる可能性もあります。
施工不良の場合、改めて修理を依頼する必要があります。
かえって費用が高くつく恐れがあるため注意しましょう。
業者が手抜き工事やミスをしたため、新築やリフォーム直後でも雨漏りするケースもあるので注意が必要です。
費用を抑えたいからと、料金の安い業者を選ぶと手抜き工事が行われる可能性もあります。
施工不良の場合、改めて修理を依頼する必要があります。
かえって費用が高くつく恐れがあるため注意しましょう。
屋根の雨漏りを修理せず放置するリスク

二次被害には次のようなものがあります。
・腐食により住宅の耐久性が低下する
・クロスが剥がれたりシミが発生したりする
・白アリやカビが発生する
・家族の健康が損なわれる
・漏電、感電や火災の恐れがある
どのような被害か、一つずつ見ていきましょう。
腐食により住宅の耐久性が低下する
屋根から浸入した雨水が柱や梁などに伝わると、腐食を引き起こし住宅の耐久性が低下してしまいます。
その結果、建物が傾いたり天井が落ちたりする危険性も出てきます。
鉄筋コンクリートの建物でも、雨漏りによる腐食が発生する可能性があるため、注意が必要です。
雨漏りは自然に直るものではありません。
放置すればどんどん進行していくため、時間が経つほど危険性は高まります。
その結果、建物が傾いたり天井が落ちたりする危険性も出てきます。
鉄筋コンクリートの建物でも、雨漏りによる腐食が発生する可能性があるため、注意が必要です。
雨漏りは自然に直るものではありません。
放置すればどんどん進行していくため、時間が経つほど危険性は高まります。
クロスが剥がれたりシミが発生したりする
雨漏りによって室内にまで雨水が浸入してくると、クロスが剥がれたり、シミが発生したりします。
目に見える形で影響が出ている段階で、建物の内部にはカビが大量発生している可能性があります。
一時的にクロスを取り替えたりシミを消したりしても、根本的な解決にはなりません。
室内の湿度が高い・カビ臭さを感じる、といった異変が発生している時点で、建物の腐食が始まっている可能性もあります。
目に見える形で影響が出ている段階で、建物の内部にはカビが大量発生している可能性があります。
一時的にクロスを取り替えたりシミを消したりしても、根本的な解決にはなりません。
室内の湿度が高い・カビ臭さを感じる、といった異変が発生している時点で、建物の腐食が始まっている可能性もあります。
白アリやカビが発生する
雨漏りの影響で室内の湿度が上がると、白アリやカビが発生します。
白アリは湿った木材を好むため、腐食した柱や梁を食い荒らし、中身がスカスカの状態になります。
雨水で腐食しているところに、さらに白アリが繁殖すれば、住宅の耐久性はますます低下するでしょう。
白アリの被害は見えない場所で進行するため、トラブルに気づきにくいのも厄介な点です。
白アリ同様、カビも高温多湿の場所を好むため、雨漏りで湿度の高くなった環境で大量発生する可能性があります。
白アリは湿った木材を好むため、腐食した柱や梁を食い荒らし、中身がスカスカの状態になります。
雨水で腐食しているところに、さらに白アリが繁殖すれば、住宅の耐久性はますます低下するでしょう。
白アリの被害は見えない場所で進行するため、トラブルに気づきにくいのも厄介な点です。
白アリ同様、カビも高温多湿の場所を好むため、雨漏りで湿度の高くなった環境で大量発生する可能性があります。
家族の健康が損なわれる
雨漏りの影響でカビが発生すると、クロスの汚れだけでなく健康被害の心配も出てきます。
カビが繁殖している空間で生活していると、呼吸の度にカビを吸い込んでいる状態になってしまうのです。
カビが原因で起こる病気には、以下のようなものがあります。
・アスペルギルス症
・過敏性肺炎
・喘息
・アトピー性皮膚炎
・シックハウス症候群
必ず発症するとは限りませんが、小さなお子さんやお年寄りは体調を崩す可能性が高いといわれています。
ご家族の体調を守るためにも、雨漏りの放置は控えましょう。
カビが繁殖している空間で生活していると、呼吸の度にカビを吸い込んでいる状態になってしまうのです。
カビが原因で起こる病気には、以下のようなものがあります。
・アスペルギルス症
・過敏性肺炎
・喘息
・アトピー性皮膚炎
・シックハウス症候群
必ず発症するとは限りませんが、小さなお子さんやお年寄りは体調を崩す可能性が高いといわれています。
ご家族の体調を守るためにも、雨漏りの放置は控えましょう。
漏電・感電や火災の恐れがある
家具や家電が濡れた場合、新しいものに買い換える必要があり、雨漏りの修理以外にも費用がかかってしまいます。
雨水でブレーカーやコンセントなどが濡れると、漏電・感電の危険性も出てきます。
漏電時の火花がホコリに引火し、火災が発生する可能性もあります。
雨水でブレーカーやコンセントなどが濡れると、漏電・感電の危険性も出てきます。
漏電時の火花がホコリに引火し、火災が発生する可能性もあります。
屋根の雨漏り修理が必要なサイン

雨漏りのサインをみつけたら、早めに業者に調査を依頼しましょう。
雨漏りのサインには、次のようなものがあります。
・天井や壁にシミができている
・天井から水滴が落ちてくる
・家の空気がカビ臭い
・雨が降るとポタポタと水音がする
雨漏りはDIYでの修理が難しく、素人では一時的な対処になると考えましょう。
かえって不具合を悪化させ、修理費用が高くなる可能性もあります。
雨漏りが発生しているかもしれないと感じたら、すぐに業者に連絡すると安心です。
特に屋根のような高い場所は、慣れない素人が上がるだけでも危険です。
屋根の雨漏り修理は信頼できる業者に依頼しよう

屋根などの高い場所は様子を見るだけでも危険が伴うため、無理をせず業者に依頼しましょう。
屋根や雨漏りの修理では、高額な費用を請求する悪徳業者にも注意が必要です。
基本的には、自分で依頼した業者以外の調査・修理の申し出は、受けない方が無難です。
作業者の資格や施工実績、口コミなどを見て信頼できる業者をみつけましょう。
▼関連記事
屋根の雨漏り修理費用が変動する要素は?調査方法や業者の選び方も解説
雨漏り修理に利用できる補助金・助成金はある?申請方法や注意点を解説
雨漏り修理の業者の選び方のポイントは?応急処置の方法も解説!